ベトナムと言えば、近年Web3の発展が目覚ましい国として名を馳せているイメージがありますが、過去に比べて、かなり多くの日本人が滞在、または移住するようになりました。
多くの日本人は企業の駐在員であったり、フリーランスで現地に滞在したり、また、リタイア組としてベトナムに居住する場合が多いですが、一体、現地ではどのように資産運用をしているのでしょうか?
ここでは、ベトナム在住の日本人が、ベトナムで投資や資産運用をどのようにマネジメントしているのかをご紹介します。
投資・資産運用の主な手段は?
日本国内の証券口座を利用する
多くのベトナム在住者は、日本の証券会社口座を使って、日本に居たときと同じ環境で、引き続き、国内株式やETF、FX、投資信託などに投資しています。
例えば、Plus500で日本で取引することもそうですが、世界でも有数のサイバーセキュリティと危機管理を徹底している日本の証券会社や暗号資産取引所を利用することで、ベトナムにいても同様のサービスを継続して受けることができます。
もちろん、日本で人気の高いNISAの口座やそれ以外の投資銘柄の特定口座でも、ベトナムで安心して継続的に管理することができます。
ここで気に留めておくべき点は、マイナンバーのあり方を改めて認識すること、そして非居住者として扱われるという意識を高めておくことです。投資や資産運用は日本国内にいる時と同じように続きますが、あくまで日本を離れて生活をしている身であることを忘れないようにしましょう。
暗号資産に投資をする
ベトナムでは暗号資産(仮想通貨)への関心が非常に高いです。実際、2026年から、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を代表するデジタル資産を正式に合法化する予定であるため、ベトナム国民にとっても、より投資への関心が広がることが期待されています。
日本国内でも金融庁に認可された暗号資産取引所がいくつかありますが、日本人投資家の中には海外に拠点を持つグローバル取引所を積極的に活用している傾向が強まってきました。
日本でも2020年を境に暗号資産への関心が高まりつつあり、さらに米国のトランプ大統領の暗号資産への熱意やイニシアチブが報道されて以来、その過熱ぶりは顕著だと言えます。
また、暗号資産においては、受動的な利益を受けられるステーキングやDeFiなども取り入れて、資産を効果的に増やしていく工夫をしています。これは、ベトナムに住む日本人のみならず、世界の国や地域で暗号資産への投資をしている人たちが行っている、比較的手堅い投資手段です。
NFTに投資をする
海外の有名スポーツ選手のカードコレクション、そして世界に広がるさまざまなアーティストが手掛けるNFTコレクションに投資をし、価値が高まるのを狙う日本人も多くいます。最近では、ベトナムのラッパーが最新アルバムをNFTで販売するなど、ベトナムのWEB3への挑戦やデジタル産業で世界で台頭していこうとする意気込みが顕著にみられます。
ベトナム国内の不動産や株式投資を実施する
ベトナム在住の日本人でも、法律上はベトナムの不動産や株に投資することできることになっています。しかし、これには法的な制限や手続きが多いため、現地に信頼できるパートナーがいることが前提になります。
投資と資産運用の管理、そのコツとは?
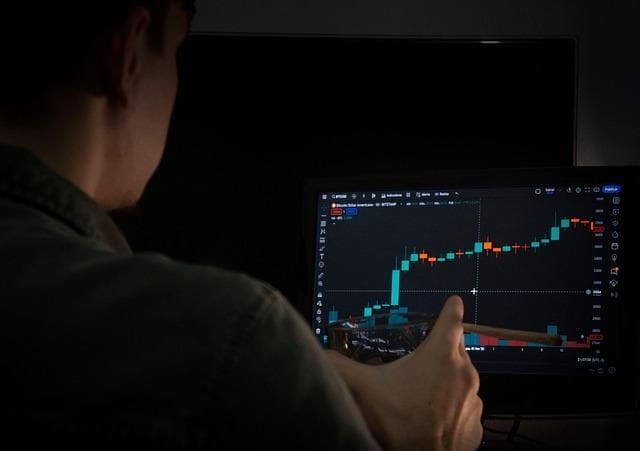
通貨を分散し、為替のリスクを徹底管理する
ベトナム在住の日本人投資家は、日本円、米ドル、ベトナムドンといった外貨を分けて保有する方が多く、こうすることで、為替変動リスクを分散しています。例えば、圧倒的に強いドル建ての資産を多めに持ちつながら、ベトナムドンでの支出に備えて流動性を確保しているようなイメージです。ベトナムにいても、やはり為替による「リスク管理」は最重要項目でしょう。
日本への送金を賢く行い、二重課税を避ける
ベトナムから日本への送金には上限や審査があります。そのため、現地の日本人は、ベトナム国内の銀行(TPBank、Techcombankなど)やWISEといった信頼性の高い国際送金サービスを賢く使い、定期的に資金移動を行うようにしています。
また、税金関連についても、日本での確定申告や非居住者扱いの確認を行い、二重課税を避ける工夫をしています。
まとめ
ベトナムにおいては、1~6月期の海外派遣労働者数7.5万人、日本向けが最多3.5万人となっており、ベトナムと日本のつながりが一層強まっています。
ベトナム在住の日本人が資産運用をする際は、分散投資とリスク管理を意識した戦略をとることが重要ですが、同様に、税務・法律における知識も不可欠です。現地の日本人のネットワークを有効的に活用しながら、アップデートされた投資・資産運用に関する情報を正しく取り入れ、自分に合った投資スタイルを見つけるようにしましょう。


